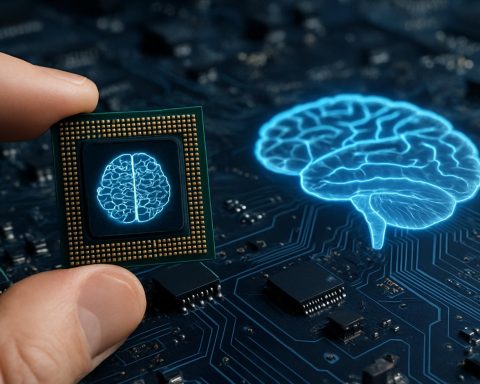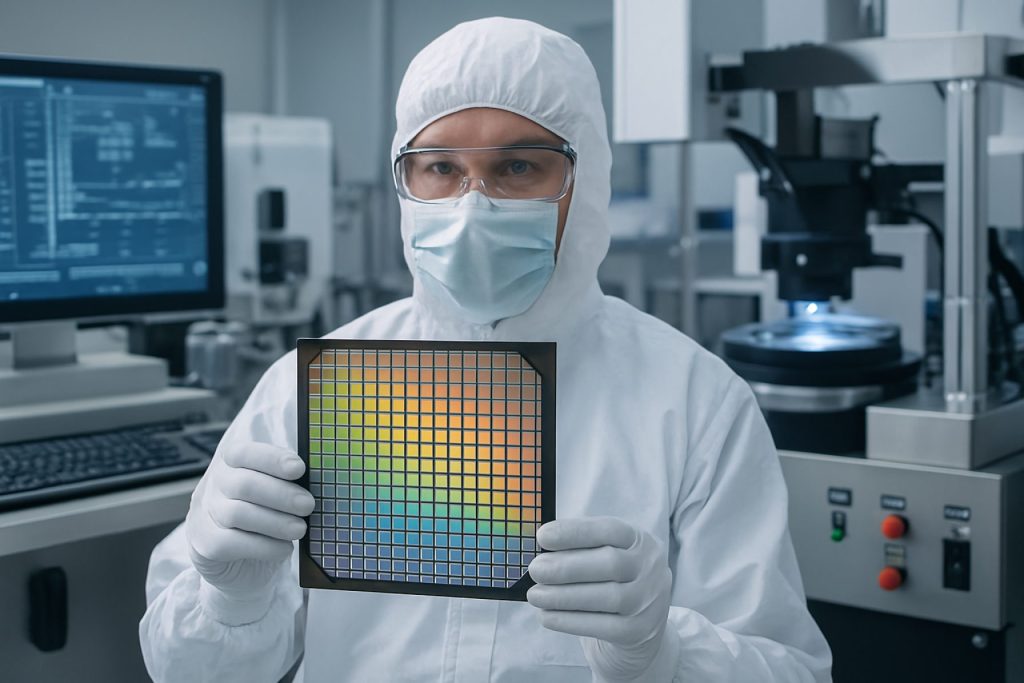ゆず認証の革新:2025年から2030年にかけての専門家の予測
目次
- 概要:2025年の審査付きゆず認証の状況
- ゆず認証を変える主要ドライバーと市場の力
- 新興認証技術:ゲノム、AI、およびトレーサビリティ
- 規制基準と業界の取り組み(2025〜2030年)
- 主要プレイヤー:リーディング生産者、認証機関、技術提供者
- ケーススタディ:主要な審査付きゆず市場での成功した実施例
- 市場規模、成長予測、2030年までの予測
- 課題:詐欺、誤表示、およびサプライチェーンの整合性
- 機会:プレミアム化、輸出拡大、消費者の信頼
- 将来の展望:革新、パートナーシップ、長期的な業界への影響
- 参考文献
概要:2025年の審査付きゆず認証の状況
2025年の審査付きゆず品種認証の状況は、主に食料品、飲料、化粧品業界における検証済み高品質ゆずへの世界的な需要の高まりによって変容しています。日本はゆず生産の中心地であり、品種認証手法の主要なイノベーターでもあります。ゆずの商業的価値が高まるにつれ、詐欺を防止し、知的財産を保護し、プレミアム市場の地位を確保するための信頼性の高い認証の重要性も増しています。
2025年には、日本の主要な農業協同組合や貿易団体(例えば、農業協同組合(JAグループ))が、 Kochi や Tokushima などの主要なゆず生産地域での審査付き認証メカニズムの採用を強化しました。これらのメカニズムは通常、認定専門家による感覚評価と分子および遺伝子テストを組み合わせて、品種の起源と純度を確認します。Kochi県ゆず振興協会は、登録された生産者に周期的な評価のためにサンプルを提出することを求める審査付き認証プログラムを拡大し、この地域のプレミアムゆずの評価を高めています。
技術の進展が認証の未来を形作っています。2025年には、生産者や加工業者が農業技術企業と提携してDNAベースの品種識別を実施し、主観性を低減し、信頼性を高めています。例えば、カゴメ株式会社や公的機関との共同研究イニシアチブは、審査付き評価と耐改ざんのデジタル記録を統合したブロックチェーンベースのトレーサビリティシステムのパイロットを行っており、透明性のあるエンドツーエンドのサプライチェーンの検証への道を開いています。
日本以外でも、真正なゆず品種への国際的な関心が高まっています。ヨーロッパや北アメリカの輸入業者やプレミアム食品ブランドは、厳格なラベリングおよび起源要件を遵守するために検証済みのゆず供給源を探しています。フランスの食品の真正性連盟などの組織は、日本の標準機関と連携し、認証プロトコルの調和を図り、相互認証協定の探求に取り組んでいます。
今後数年間を見越すと、トレンドはデジタル統合の拡大と審査付きゆず認証基準の国際的調和を指し示しています。業界の専門家は、2027年までにDNAによる品種認証が輸出基準のゆずの標準となり、デジタル認証プラットフォームが広く採用されて国際貿易を促進すると予測しています。日本の生産者グループ、外国の輸入業者、技術提供者による協力的な取り組みが、国際的なゆず市場の整合性と価値をさらに守ると期待されています。
ゆず認証を変える主要ドライバーと市場の力
ゆず品種の認証は、2025年には高度な分析技術、規制上の要請、および世界的な市場ダイナミクスが融合して、大きな変化を遂げています。特にプレミアム食品、飲料、化粧品業界において、ゆずの果実、ジュース、およびその派生品の需要が高まる中で、利害関係者は製品の整合性を確保し、地域ブランド(「日本のゆず」など)を維持し、混ぜ物に対抗するために信頼できる品種認証を優先しています。
- 規制および地理的表示:2025年、日本の農林水産省(MAFF)は、特にKochiおよびTokushimaのようなプレミアム品種を保護するために、ゆずの地理的表示(GI)制度を引き続き施行しています。この規制フレームワークは、厳格な品種認証を義務付けており、輸出業者はGIステータスを取得するために品種の系譜と生産地域を文書化する必要があります(農林水産省)。
- 技術革新: DNAバイオロギングや分子マーカ技術は、認証プロセスの中心的な役割を果たしています。いくつかの日本の農業コンソーシアムは、バイオテクノロジー企業と協力して迅速かつコスト効率の高い遺伝子タイピングアッセイを精緻化しています。例えば、農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)は、DNAベースの識別プロトコルを標準化するプロジェクトをリードし、今後2年間で生産者や輸出業者の間で広く採用されることを目指しています。
- 業界のコラボレーションと認証:主要なゆず協同組合(例:JA Kochi)は、遺伝子テストと専門的な感覚評価を組み合わせた第三者の審査パネルを実施しています。これらのパネルは、透明で監査可能な認証のモデルとして機能し、2026年までには輸出認証プログラムに統合されることが期待されています。
- 国際貿易と消費者の期待:ゆずの輸出がEU、北アメリカ、東南アジアに拡大する中、輸入業者は信頼できる証拠の提供を求めています。EUのGI相当性プロセスや食品安全当局からの監視の強化が、日本や韓国の生産者にトレーサビリティと認証システムの改善を促しています(農林水産省)。
今後数年の間に、デジタルトレーサビリティプラットフォームが審査付きゆず認証ワークフローにさらに統合される見通しです。これらの革新は、コンプライアンスの効率化、消費者の信頼の強化、真正なゆず品種に対するプレミアム価格の支持を支援すると見込まれています。生産者から世界の小売業者まで、バリューチェーン全体の利害関係者が、競争力を保ち、市場環境の変化に対応するためにこれらのシステムの導入を加速する可能性があります。
新興認証技術:ゲノム、AI、およびトレーサビリティ
2025年、審査付きゆず品種の認証は、ゲノム、人工知能(AI)、およびデジタルトレーサビリティシステムの統合によって急速に進展しています。これらの技術は、特に日本、韓国、および新興輸出先のプレミアムゆず市場の整合性を維持するために、品種の特定、出所の確認、および品質保証に関する長年の業界の課題に取り組んでいます。
ゲノム認証は、品種確認の基盤となっています。主要な農業研究機関や育苗業者は、次世代シーケンシング(NGS)や単一ヌクレオチド多型(SNP)マーカ解析を使用して、真のゆず(Citrus junos)をハイブリッドや関連する柑橘類から区別しています。例えば、日本の農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)と韓国森林研究院は、認証されたゆず品種の参照データベースを作成するためにDNAバイオロギングプロトコルを精緻化しています。これらのゲノムライブラリは、育種権や知的財産の保護をサポートするだけでなく、透明性のある検証を求める育苗業者や加工業者に対して耐改ざんの資源を提供します。
AI駆動の画像分析は、選別センターや育苗業者での果実や葉の迅速かつ非破壊的な特定に活用されています。キュレーションされたゆずデータセットでトレーニングされた機械ビジョンシステムは、微妙な形態的特徴に基づいて品種を信頼性高く区別できるようになり、遺伝子テストを補完します。例えば、ファナック株式会社は、ゆずの特定をリアルタイムで統合するAIベースの選別ラインを試行するために農業協同組合と協力しています。
ブロックチェーンとQRコードのタグ付けを利用したデジタルトレーサビリティプラットフォームは、ゆずの生産者や輸出業者の間で導入が進んでいます。これらのシステムは、苗木の増殖から農場管理、加工、輸出までのエンドツーエンドの追跡が可能であり、起源地点で認証された品種のアイデンティティがサプライチェーン全体で保持されることを保証します。日本の日本ゆず協会と主要な包装業者が、ヨーロッパや北アメリカのバイヤーがモバイルデバイスを通じて認証された品種データにアクセスできるようにするパイロットプロジェクトを展開しています,而これは信頼と出所の主張を強化しています。
今後は、ゲノム、AI、トレーサビリティの融合が、2027年までに審査付きゆず認証の標準になると期待されています。規制機関や業界団体は、これらの技術に基づく認証スキームを正式化することが期待されており、リアルタイムの検証用のリモートセンシングやIoTの統合が進行中です。特産柑橘類の真正性への消費者の需要が高まる中で、これらの革新は、世界的なゆず市場の生産者と消費者を保護する上で重要な役割を果たします。
規制基準と業界の取り組み(2025〜2030年)
2025年以降、審査付きゆず品種の認証に関する規制基準と業界の取り組みが大きな進展を遂げることが予想されます。真正なゆず製品への世界的な需要が引き続き高まる中、日本は商業的なゆず生産の発祥地であり主要な供給源として、これらの取り組みに最前線で関与しています。複数の利害関係者が協力してトレーサビリティと品種確認メカニズムの強化に取り組んでいます。
2025年には、日本の農林水産省(農林水産省)が、地理的表示(GI)保護のフレームワークを強化しています。GI制度は、すでにKochiやTokushimaなどのゆず生産地域を対象としており、認証されたゆず品種に対して厳格な文書化とデジタルトレーサビリティを義務化するために更新されています。これには、指定された条件下で栽培されたものでなければならず、そのためのブロックチェーンベースの帳簿やDNAベースの認証プロトコルの使用が含まれます。
日本ゆず協会などの業界団体は、主要なゆず品種に対してDNA指紋キットを開発および標準化するために学術機関と共同作業を行っています。これらのキットは現在、選択された生産者でパイロット実施されており、2026年までにはGI認証の要件となる見込みです。この遺伝子による認証は、誤表示を防止し、国内市場と輸出市場の純度を確保することを目的としています。さらに、これらの取り組みは、日本貿易振興機構の支援を受けており、ゆず製品の輸出入文書の厳格化を実施することで、消費者の信頼を高め、日本のゆずブランドを国際的に保護しています。
- 輸出市場のコンプライアンス:特に欧州連合や北アメリカなど、いくつかの主要な輸入者が、ゆずの輸入に対して品種認証の確認できる証拠を求めています。これには、登録された農園にまでさかのぼるバッチレベルのトレーサビリティや、品種の純度のための実験室での認証が含まれます。
- 技術の統合:2027年までに、ヤンマー株式会社のような主要な日本の農業機器メーカーは、果樹管理システムを統合して提供し、生産者がサプライチェーン全体で品種認証データをシームレスに記録し共有できるようにする予定です。
- 共同研究開発:農業・食品産業技術総合研究機構と民間セクターのパートナーとの共同研究プログラムは、自動化された迅速な遺伝子認証技術の精緻化に焦点を合わせており、コストを削減し採用率を高めることを目指しています。
2030年に向けた展望は、日本の認証された生産者や輸出業者の間で、標準化された審査付きゆず品種認証がほぼ普遍的に採用されることです。これは、世界中で本物の日本のゆずの評判と市場価値をさらに高め、他の特産柑橘類の分野における規制のベンチマークを設定することが期待されています。
主要プレイヤー:リーディング生産者、認証機関、技術提供者
2025年の審査付きゆず品種認証の状況は、品種の整合性とトレーサビリティを確保するために働く、確立された生産者、認証機関、および新興技術提供者によって形成されています。真正なゆずへの世界的な需要が高まる中(特に北アメリカとヨーロッパで)、これらのプレイヤーは品質と出所の基準を維持する上で重要な役割を果たします。
- 主な生産者:ゆず生産の中心地である日本では、Kochi県のKitayama Yuzuや、JA Kochi県などの協同組合が、真正なゆず栽培の基準を設定し続けています。これらの団体は厳格な内部プロトコルを開発し、遺伝的、形状的、官能的なプロファイルに基づいて品種を審査する地域プログラムに参加しています。
- 認証および認証機関:日本の農林水産省(MAFF)は、主要な規制当局であり、品種の登録を維持し、ゆずの地理的表示(GI)の保護を施行しています。MAFFのGIプログラムは、Kitagawa、Gojo、Umajiなどの地域を対象としており、認証プロトコルの一環として審査パネルの評価とDNA検証を義務付けています。日本国外では、アメリカ合衆国農務省動植物検疫局(USDA APHIS)が、日本の認証機関と連携してゆずの輸入を検証しており、2025年には品種認証のための新しいパイロットプログラムが展開されます。
- 技術提供者:遺伝子バイオロギングおよびブロックチェーンベースのトレーサビリティの採用が加速しています。日東電工株式会社のような企業は、現場での品種認証のために日本の協同組合によって試行されています。また、富士通株式会社は、Kochiの生産者やMAFFとの協力で、苗木から輸出までの品種データを確保することを目的としたブロックチェーン支援プラットフォームの試行を行っています。2026年までに完全導入の計画があります。
- 展望:今後数年の間に、確立された生産者、認証機関、技術革新者との相互作用が、審査付きゆず認証のためのより強固でスケーラブルなシステムを生み出すことが期待されています。越境貿易の増加と新しい栽培地域へのゆず品種の普及が、標準化された技術駆動の認証へのさらに多くの投資を促進する可能性があります。これは、日本の業界団体のリーダーシップによって支えられ、国際的な規制の調和に寄与するでしょう。
ケーススタディ:主要な審査付きゆず市場での成功した実施例
2025年には、審査付きシステムによるゆず品種の認証が、日本、韓国、および特定の欧州連合加盟国の主要市場で重要な進展を遂げています。これらのシステムは、品種の純度を保証し、詐欺的なラベリングを防ぎ、生産者と消費者の双方を保護するために、ゆず製品の起源と遺伝的整合性を認証しています。
日本は、地域の農業協同組合や政府の監視に支えられて、審査付きゆず認証の最前線にあります。農業・食品産業技術総合研究機構(MAFF)は、ゆず品種のGI制度を監督しており、KochiやTokushimaの地域からのゆず品種は、遺伝子マーカ解析と多層の審査によって認証されています。2024年までに、これらの県からのゆず輸出の60%以上がGI認証を受けており、過去3年間で認証された量の増加を反映しています。この成功は、デジタルトレーサビリティプラットフォームの導入と、JA Kochi農業協同組合連合会などの地域生産者ユニオンとの協力によるものです。これによって、厳格な品種基準の遵守を支援しています。
韓国では、農林水産食品貿易公社(aT)が2023年に審査付き認証フレームワークを立ち上げ、Goheung地域のゆずに焦点を当てています。このフレームワークは、DNAプロファイリングと現地での審査検査を統合し、本物のGoheungゆずのみが輸出チャネルに到達することを保証します。初期の結果は、韓国のゆずに対する誤表示の事例が40%減少し、2026年までに認証された生産者の数が25%増加する見込みです。
欧州連合は、地理的表示保護制度(PDO)の下で認証されたゆずの初回輸入を開始し、日本の当局や専門的な輸入業者と密接に協力しています。例えば、FreshPlaza Europeポータルは、GI認証を受けたKochiゆずがフランスやイタリアのグルメ流通業者に成功裏に出荷されたことを記録しており、各バッチを検証する独立した審査パネルがデジタル証明書をサポートしています。
今後数年間の展望は、消費者の透明性とプレミアム化への需要に駆動され、審査付きゆず認証が引き続き拡大することを示しています。日本のMAFFは、2027年までにGI登録されたゆず品種の数を倍増させることを目指しており、韓国のaTはさらなる詐欺防止のためにブロックチェーンベースの文書を導入する計画です。EUは、2026年までにPDOゆずの本格的な輸入を承認すると予想されており、国際的な認証基準のベンチマークを設定することになります。
市場規模、成長予測、2030年までの予測
審査付きゆず品種認証を対象とした世界市場は、検証済みの高品質のゆずへの需要が高まる中で、強固な成長のフェーズに入っています。特に食品、飲料、化粧品業界において、2025年までに、遺伝的、形態的、出所に基づくメソッドを使用するゆず品種の認証が、規制コンプライアンス、プレミアム製品の差別化、詐欺防止においてますます重要になっています。
日本はゆず生産と認証イニシアチブの中心地です。国内のゆずの生産量は年間27,000トンを超え、厳格なラベリング基準と、Kōchi や Tokushima ゆずなどの地域品種の地理的表示(GI)ステータスの追求によって、品種認証の必要性が高まっています。日本の農林水産省(MAFF)のような組織は、認証プロトコルとGI保護のための支援を拡大し、トレーサビリティと品種確認システムのための規制の基盤を提供しています。
2025年には、業界の投資が日本と韓国、オーストラリアなどの輸出国で加速しています。例えば、タキイ種苗株式会社やサカタのタネ株式会社は、国際的なバイヤーからの需要の高まりに応じて、育苗業者や商業生産者向けに遺伝子検査サービスを強化しています。同時に、韓国の輸出業者は、農林水産食品貿易公社(aT)と協力して、ヨーロッパと北アメリカ市場での信頼性を高めるために、ブロックチェーンベースのゆずトレーサビリティおよび認証プログラムを試行しています。
アナリストは、審査付きゆず品種認証セクターが2030年までに高い一桁台の年間成長率(CAGR)を達成し、市場規模はグローバルなゆず貿易と平行して拡大する見込みです。2030年までに、日本からの認証されたゆずの輸出価値が10億円を超えると、日本植物防疫協会の見積もりによれば予測されています。この成長は、トレーサブルで認証された成分に対する消費者の好みの高まりと、GI登録および起源証明を義務付けるEUのような市場における厳格な輸入管理によって支えられています。
- デジタル認証プラットフォームとDNA指紋技術の拡大により、品種確認の効率化、コスト削減、スケーラビリティの向上が期待されています。
- 日本、韓国、オーストラリアの関係者間でのクロスボーダーコラボレーションが、認証プロトコルの標準化を促進し、市場成長を刺激することでしょう。
- 政策の進展、特にGI登録や詐欺防止の実施が、今後5年にわたって市場参入条件を形成し、認証ソリューションへの投資に影響を与えるでしょう。
まとめると、2030年までに審査付きゆず品種認証市場は、規制上の要請、技術革新、そして世界中のゆずベース製品のプレミアム化によって、持続的な成長が見込まれています。
課題:詐欺、誤表示、およびサプライチェーンの整合性
ゆずの需要が急増している中で、特に日本、ヨーロッパ、北アメリカなどの高価値市場では、詐欺、誤表示、サプライチェーンの整合性に関する課題が顕著になっています。真正なゆず品種がその独特の香りや風味のプロファイルによりプレミアム価格を要求する中で、偽造や誤表記されたゆず製品が増加しています。これにより、品種の整合性と消費者の信頼を保持するために堅固な審査付き認証メカニズムが必要とされています。
2025年には、KochiやTokushimaなどの主要な日本のゆず生産県が、自らのゆず品種の認証を守る努力を続けています。これらの地域では、指定された品種の名称と起源を法的に保護する地理的表示(GI)システムが導入されています。しかし、GIの保護は国際的な執行において課題に直面しています。特に輸出が増える中で、ゆず由来の製品がその地域の外で混合されたり、再包装されたり、ラベルが変更されたりすることが多く、問題となっています(農林水産省)。
小規模な農場、協同組合、加工業者、仲介業者、国際的な流通業者など、サプライチェーンの複雑さがトレーサビリティをさらに難しくしています。これに応じて、日本の業界リーダーたちは、品種の系譜や取引履歴を各段階で文書化するために、ブロックチェーンベースの記録などのデジタルトレーサビリティシステムを導入し始めています。たとえば、Kochi県農業協同組合は、購入者がゆずのバッチが由来する農園やロットを確認できるQRコードラベリングを試行しています。これは、審査付きの第三者認証パネルによってサポートされています。
これらの進展にもかかわらず、いくつかの持続的な課題が残ります。 adulteration の問題、すなわち他の柑橘類との希釈や合成香料の使用は、特にジュースやオイル、調味料のような加工製品では検出が難しい場合があります。DNAバーコーディングや高度なメタボロミクプロファイリングを使用した科学的品種認証が商業的に展開されつつありますが、コストや包括的な参照ライブラリへのアクセスに制限されています(農業・食品産業技術総合研究機構)。業界団体は、これらの方法論の標準化に向けて協力しており、2027年までのより広範な導入を目指しています。
今後の展望として、規制フレームワーク、技術革新、および業界の協力がゆず品種認証のプロトコルを強化すると期待されています。利害関係者は、数年以内に、デジタルトレーサビリティ、審査付き認証、および分子分析の組み合わせがこの分野の標準となり、詐欺のリスクを減少させ、世界中の本物のゆずに対するサプライチェーンの整合性を確保することができると見込んでいます。
機会:プレミアム化、輸出拡大、消費者の信頼
審査付きゆず品種認証は、ゆず製品のプレミアム化と輸出拡大の重要な要因として浮上しており、消費者の信頼と業界の透明性に直接影響を与えています。2025年には、世界的なゆずの需要が高まる中で、 robust authenticity verification を確保するためにいくつかのイニシアチブと技術的進展が導入されています。
日本は世界の主要なゆず生産国かつ輸出国として、地域ブランドを保護し、製品の整合性を保証するために品種認証の努力を強化しています。業界団体や生産者協同組合(例:日本ゆず協会)は、従来の感覚評価パネルと現代の遺伝子検査を組み合わせた審査付き認証プロトコルを実施しています。これらの措置により、貴重な「Kochi Yuzu」などの指定された品種のみが、地理的表示(PGI)やその他のプレミアムラベルを取得できるようになります。
技術提供者や農業研究機関は、DNA指紋、同位体分析、およびブロックチェーン対応のトレーサビリティを展開するために共同で取り組んでいます。例えば、サカタのタネ株式会社は、標準化された品種識別キットを開発し、農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)は、関連する柑橘類の中から真正なゆずを区別するための分子マーカ技術を進めています。これらのツールは、誤表示や詐欺が信頼を損なったり、規制の障壁を生んだりすることがある厳しい海外市場へのアクセスを目指す輸出業者にとって重要です。
国際的なバイヤーや目の肥えた消費者にとって、審査付き認証は、出所、品種の純度、および生産方法を保証します。日本の大手輸出業者であるマルハニチロ株式会社は、審査付きの認証や透明なサプライチェーンの文書をゆず提供に組み込んでおり、これらの証明書を利用してプレミアム価格を正当化し、新しい輸出契約を確保しています。
- プレミアム化:認証された認証は、高価値の特産ゆず製品の位置づけを支援し、グルメ食品、飲料、化粧品の成長を促進します。
- 輸出拡大:外国の認証基準に準拠することで、新しい市場への参入を容易にし、貿易紛争のリスクを低減します。
- 消費者信頼:透明性のある審査付きの認証は、消費者に品質と倫理的な調達を保証し、ブランドの忠誠心を育む役割を果たします。
今後、デジタル検証と認証基準の国際的な整合性が、2026年以降、プレミアムな日本および世界のゆず関連の利害関係者にさらなる機会を提供することが期待されています。
将来の展望:革新、パートナーシップ、長期的な業界への影響
審査付きゆず品種認証の未来は、2025年およびその直後の年に顕著な進化を遂げる準備ができています。これは、技術革新、戦略的なコラボレーション、特産柑橘類市場における出所と真正性の重要性の高まりに駆動されています。ゆずの世界的な人気が急増する中で、特にプレミアム食品、飲料、化粧品セクターにおいて、品種のアイデンティティと地理的起源の厳格な確認に対する需要がますます高まってきています。
革新の主要な分野は、高度な遺伝子および分子マーカ解析の普及にあります。2025年には、主要な日本の農業協同組合や研究機関が、DNAバイオロギングやSNP遺伝子型分析の使用を拡大し、貴重な「Yuko」や「Kito」品種などの真正なゆず品種を識別し、潜在的な偽者やハイブリッドと区別することに取り組んでいます。JA全農や農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)などの組織がこの取り組みを主導し、次世代シーケンシングを活用して認証された遺伝的プロファイルを作成し、審査付き認証プロセスで参照できるようにしています。
業界のパートナーシップも進展の特徴となっています。2025年には、日本の生産者、認証機関、国際的な輸入業者の間で、第三者認証とデジタルトレーサビリティのプロトコルが公式化される新しい同盟が結成されています。日本の農林水産省(MAFF)が主導するプログラムでは、特定のゆず生産地域に対する公式な地理的表示(GI)のラベル付けが確立され、GOI認証が付与される前に審査パネルによって品種の純度とテロワールの主張を検証する必要があります。これらの取り組みは、国内および海外市場で保護された地位を求めるために、より多くの地域や品種に拡大する見込みです。
長期的には、業界に与える影響は変革的なものになると見込まれています。現在、日本のいくつかの柑橘協同組合によって試験的に導入されているブロックチェーンベースのトレーサビリティの統合は、すべてのゆず生産の各段階と認証された品種データを結びつける不変の記録をもたらす可能性を秘めています。これにより、詐欺から保護されるだけでなく、消費者の信頼が高まり、認証された製品に対するプレミアム価格が支持されます。GLOBALG.A.P.が日本の輸出業者と連携して導入する標準化されたデジタル認証プラットフォームは、柑橘類の認証に関する新しい国際基準を設定すると期待されています。
今後に向けて、科学的厳密さ、デジタルインフラ、およびセクター横断的なコラボレーションが、審査付きゆず品種認証の次の時代を形作るでしょう。2027年までには、高価値輸出や保護された指定市場向けのゆずのすべてが、ほぼ普遍的に分子認証とトレーサビリティ基準を受け入れることが予想され、業界の質保証とブランドの整合性へのアプローチを根本的に再構築することになります。
参考文献
- カゴメ株式会社
- 日本の農林水産省
- 農業・食品産業技術総合研究機構
- JA Kochi
- ファナック株式会社
- 富士通株式会社
- FreshPlaza Europe
- タキイ種苗株式会社
- サカタのタネ株式会社
- GLOBALG.A.P.